TOPICSお知らせ

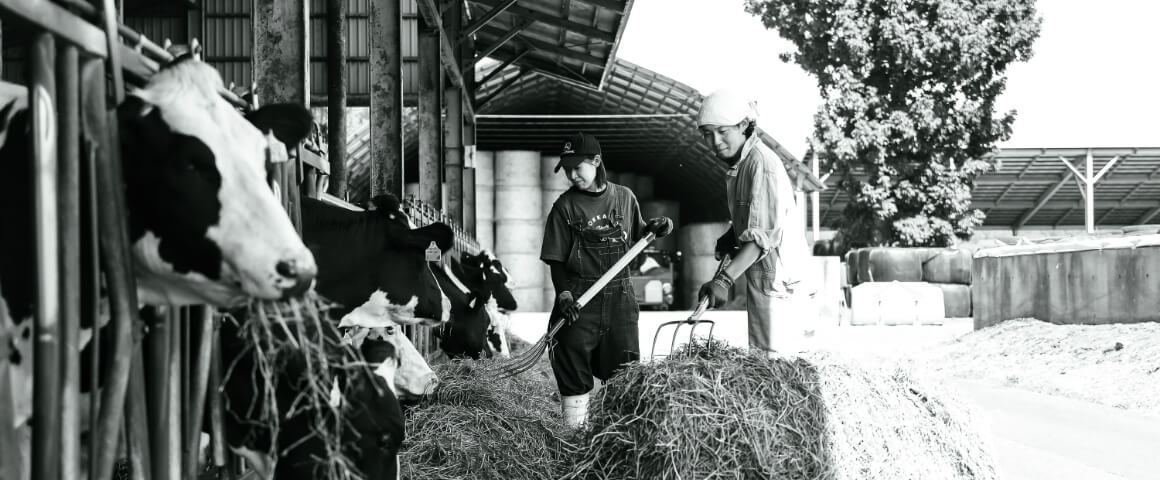
- REPORT
人が少ない地域でも、だからこそ、やれることがある。「人口減少下の新しいビジネス~縮小する地域経済を突破する挑戦~」SESSION3レポート
2025.02.21
2024年11月15日に開催された「北のアトツギカンファレンス2024」。同カンファレンスは北海道経済産業局の委託事業として開催。北海道のさまざまなアトツギ(後継者)を招き、参加者同士がマッチングすることを目的として、テーマごとにディスカッションやピッチのデモンストレーションなどを実施しました。
ディスカッションは、オホーツク地方のアトツギが登壇したSESSION1、アトツギ甲子園出場経験者がメンターの必要性について語ったSESSION2、人口減少下で家業と新規事業を掛け合わせる挑戦者たちが登壇したSESSION3の3部構成。前線で活躍する後継者たちのアグレッシブな挑戦やリアルな悩みなどが聞ける貴重な機会となりました。
https://n-northern-c.com/159/
▲SESSION1「オホーツクミドル、オホーツクを背負う跡継ぎ」
https://n-northern-c.com/173/
▲SESSION2「地域のアトツギにメンターは必要か?~アトツギ甲子園」

本記事では「SESSION3 人口減少下の新しいビジネス~縮小する地域経済を突破する挑戦~」の一部をお見せします。
地方都市の地域経済・産業が縮小の局面を迎える中、家業と新しい事業を組み合わせてシナジーを起こし、新たな付加価値を生み出しているアトツギの皆さんにご登壇いただきました。家業の未来と地域の未来をどのように捉え、地域ならではの挑戦をどう進めているのか。リアルな取り組みを伺いながら、未来へのヒントを考えていきます。
アトツギ甲子園とは?
アトツギ甲子園は中小企業庁が主催するピッチイベント。中小企業や小規模事業者の後継者(アトツギ)が新規事業アイデアを競うもの。まだ事業承継をしていない39歳未満の後継者のチャレンジや活躍を後押しし、早期の事業承継や地域経済の活性化を図ることを目的としている。
https://atotsugi-koshien.go.jp/
「地域の“弱点”を“ポジティブ”に」人口減少の捉え方

最初のテーマは「地域の人口減少をどう見ているか」について。北海道クリエイティブの代表取締役でモデレーターを務める吉田聡子さんは、北海道全体では2023年からの1年間で人口が5万6000人減少し、全国最多の減少数を12年連続で更新したという衝撃の事実に触れました。一般的には悲観的な捉え方をされがちな人口減少に、北のアトツギたちはどう向き合っているのでしょうか。

山ス伊藤商店取締役の梅木さんは、「人口がこれ以上増えないということを認めることが大事」と語ります。そんな梅木さんが掲げるのは「明るい過疎化」。
「100人の集落の中にチャレンジャーがいたら10人いれば、すごくおもしろい場所になると思います。仮に自治体がなくなってしまっても、おもしろい人がいれば地域は廃れないのではないかという考えのもと、Tsukigata LABO(つきがたラボ)というコワーキングスペースを作ったり、ローカル起業者育成プログラムを立ち上げたりしています」

吉田勝幸さん(写真左)/新聞販売店を継ぐことを決め、2004年にUターン。人口減少の煽りを受け、現在はピーク時の1万260部の約60%となり、6200部にまで減少している。
続いて株式会社五明の五明さんは、「業務用の酒の卸売りという仕事はゼロにならないとしても、人口減少の影響は無視できません。この地域でやれることを考えていかなければいけないと思っています」と語ります。
そんな五明さんが着手しているのが、宿泊施設の立ち上げ。釧路が生んだ鬼才・毛綱毅曠(もづなきこう)さんが建築した個人病院を買い取り、宿泊施設として生まれ変わらせる計画を進めています。その背景にあったのは、釧路市が持つ観光地としてのポテンシャルと、弱みである人口減少を逆手にとった発想でした。
「釧路市は北海道の中でも長期滞在しやすい地域として注目されてきており、観光客を受け入れる“箱”が必要です。一方で、人口減少によって空き家が増えてきている。この空き家を活用して宿泊施設を作ればいいのではないかと考えました。こうした自分たちの挑戦を通じて、弱点を利点として捉え直し、チャレンジする土壌を育てていきたいと考えています」
続いてマイクを持ったのは、新聞販売を主な事業としてきたマルカツの吉田さんです。人口減少の影響を受けやすく、エリア制かつ価格規定などさまざまな制約がある新聞販売業。吉田さんはその事業に限界を感じ、“新聞紙”を届けるのではなく、新聞を通じて世の中を「つなぐ」「届ける」という発想に方向転換をしたのだと話します。
その一つが「チラシ物販」という試みです。お届けする商品の製造過程や生産者の想いといったストーリーを自作のチラシに掲載して届けることで、人と人とを“つなげたい”という想いから始まった企画だそう。
「私たちが新聞を配達するエリアには、一人暮らしの方も多いんです。遠く離れて暮らすお子さんに対して『〇〇さんが作ったリンゴがおいしいからおいで」と呼ぶきっかけを作って、豊かな暮らしにつながればいいなという想いで始めました」
家業×新事業が生み出すシナジーとは?

次のテーマは「家業と新事業とのシナジー」について。
業務用の酒の卸売りを行う家業を守りながら、宿泊施設の立ち上げを機に観光業への進出を目指す株式会社五明の五明さんは、宿泊客に対して地域のお酒を集めて飲み放題にするサービスを考案。
「『地域のお酒が飲めるから、ここに泊まろう』と思ってもらえるよう、家業である酒屋だからこそ届けられるメッセージを大切にしています」
続いて土木資材の卸売りを行う山ス伊藤商店の梅木さんは、家業と新事業の関連性は薄いとしながらも「家業の“信頼”は大きい」と話します。
「地域の人の中には、私が今行っている新しい取り組みを受け入れ難いと感じている人もいると思います。でも、私の祖父が地域に根差して長く活動してくれたおかげで『梅木さんがやっているなら』と見守ってくれている。アトツギがまちづくりを行う“武器”は家業の信頼なんじゃないかとすら感じますね」
マルカツの吉田さんは、「家業である新聞販売業の売上を維持する方法を考えた結果、新事業の着想を得た」と語ります。
「もともとは新聞を読んでくれている人が健康に長生きしてくれることが売上維持につながるのではないかと考えたのがきっかけでした。そこから、人と人とのつながりやコミュニティを作る新事業の構想が膨らんでいきました」

また、コロナ禍に遠く離れた家族に釧路のおいしいものを“届ける”「クシロバコ」という新事業を立ち上げた吉田さん。その広告を北海道新聞に出稿するなど、長く歩みをともにしてきた新聞という媒体をうまく活用している点においても、家業とのシナジーが生まれていると言えるかもしれません。
新事業は地域をどのように変えてきたのか

人口減少下の地域に一石を投じるべく、新事業を立ち上げてきたアトツギたち。その挑戦によって地域はどのように変わってきたのでしょうか。
マルカツの吉田さんは、釧路産ツブを扱った事業の実体験を紹介。当初は「北海道産ツブ」という表記により、埋もれてしまっていた釧路産ツブの文化を伝えるために「さっぽろオータムフェスト」に“ツブGuy(つぶがい)”として出演するなど、自ら釧路産ツブの宣伝部長を買って出た吉田さん。その結果、情報番組や観光雑誌で大きく取り上げられ、今では「釧路ってツブが有名らしいね」という声をよく聞くようになったと言います。
酒の卸売りを行う家業を継ぎ、宿泊施設のオープンを目前に控えた五明さんは、「酒は差別化が難しい商材。付加価値をつけるかに悩んでいるところです」と正直な心境を語りました。
地域においてユニークな人材の輩出に取り組んでいる梅木さんは、「4~5年かけてようやく小さな渦が出てきたところで、あと2~3年したら爆発すると思っています」と、自身が打ち立てた事業への確かな手応えを感じていました。

アトツギ3名のトークを受けて、モデレーターの吉田さんは「人口とはあくまで『データ』で、私たちが見つめるのは『人』ですよね」と確認。そのうえで「皆さんの事業のように、地域における人を見つめて、どのようにしたらその人が幸せになれるのかを追求することが、多様な地域の多様な生き残りにつながるのではないでしょうか」と締めくくりました。
ライター:佐々木ののか
撮影:横井千春
CONTACT
