TOPICSお知らせ

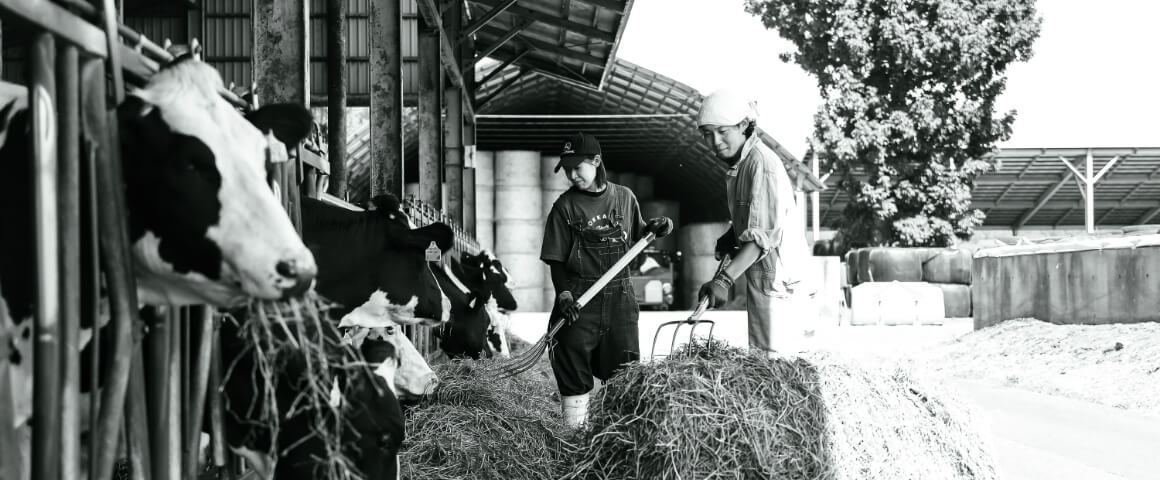
- REPORT
ピッチコンテストに出場する意義とは?メンターは必要?「北のアトツギカンファレンス2024」SESSION2レポート
2025.02.21
2024年11月15日に開催された「北のアトツギカンファレンス2024」。同カンファレンスは北海道経済産業局の委託事業として開催。北海道のさまざまなアトツギ(後継者)を招き、参加者同士がマッチングすることを目的として、テーマごとにディスカッションやピッチのデモンストレーションなどを実施しました。
ディスカッションは、オホーツク地方のアトツギが登壇したSESSION1、アトツギ甲子園出場経験者がメンターの必要性について語ったSESSION2、人口減少下で家業と新規事業を掛け合わせる挑戦者たちが登壇したSESSION3の3部構成。前線で活躍する後継者たちのアグレッシブな挑戦やリアルな悩みなどが聞ける貴重な機会となりました。
https://n-northern-c.com/159/
▲SESSION1「オホーツクミドル、オホーツクを背負う跡継ぎ」

本記事では、若手アトツギによるライトニングトークと「SESSION2 地域のアトツギにメンターは必要か?~アトツギ甲子園」の一部をお届け。
メンタリングの具体的な体験談やその際に心がけているポイント、さらに地域にメンターがいることの重要性について
アトツギ甲子園とは?
アトツギ甲子園は中小企業庁が主催するピッチイベント。中小企業や小規模事業者の後継者(アトツギ)が新規事業アイデアを競うもの。まだ事業承継をしていない39歳未満の後継者のチャレンジや活躍を後押しし、早期の事業承継や地域経済の活性化を図ることを目的としている。
https://atotsugi-koshien.go.jp/
ピッチコンテストに挑戦するメリットとは?
ピッチの後には「地域のアトツギにメンターは必要か?~アトツギ甲子園」というライトニングトークを開催。「アトツギ甲子園」への出場資格を持つ後継者の皆さんに、ピッチコンテストへの出場およびメンタリングの意義を知ってもらうことを目的としたトークです。

モデレーターを務めたのは、SESSION1でスピーカーとして登壇した山上木工の山上裕一朗さん。スピーカーは、メンタリングを受けた、あるいはメンタリングを行った経験を持つ後継者3名です。
最初のテーマは「ピッチコンテストに挑戦したきっかけ」と「挑戦後に変化したこと」について。
モデレーターの山上さんも当初は「なんのために行うのかわからなかった」というピッチコンテスト。スピーカーの皆さんはどんな出来事がきっかけで挑戦するに至ったのでしょうか。

月形・美唄・空知エリアの工事現場に向けて土木資材の販売を行う山ス伊藤商店の梅木さんは2018年に「まちづくりがしたい」という想いを胸に、前職の教員を辞職。地元に戻ってきた際に感じた孤独が、ピッチコンテストに挑戦したきっかけだったと語ります。
「地元に戻ってきたら町には人が2700人しかおらず、家業の卸売りも斜陽産業。事業の将来性も見込めず、孤独を感じていました。そんなときに日経新聞で『ベンチャー型事業承継』を対象にしたピッチコンテストの応募要項を目にしました。これまでの事業のリソースを使って新規事業を立ち上げるビジョンに胸がときめき、すぐに応募したのを覚えています」

昨年度のアトツギ甲子園に出場した水野染工場の水野さんは、現社長の父に「まだ20代で挑戦する期間が長いから1回失敗してこい」と背中を押され、“がむしゃら”に挑戦したというのがきっかけだったそう。
ピッチ挑戦後の変化については、梅木さん水野さんともに、取材の申し込みの増加や地域の人の協力が得やすくなったことを挙げ、「事業の認知度向上」や「仲間集め」にうれしい変化があったと語りました。

環境大善の窪之内さんもピッチコンテストの広告宣伝効果について「やっぱりメディアがメディアを生みますよね。予算が限られている地方において、広告戦略をどのように打つかが大事」と語りました。
そのうえで「ピッチは異種格闘技。年商も違えば、業種も違う。利益が出ているかもわからない中で、お前のアイデアに1票を投じると言われたら、こんなにうれしいことはないですよね。ぜひ参加したほうがいいですよ」と出場を後押ししました。
メンターの重要性とは?
続いてのテーマは「メンタリングの体験談」について。メンタリングを受けた、あるいは行った各々の実体験を、スピーカーたちが語りました。

梅木さんはメンタリングを受けた経験について「孤独の解消になった」と振り返ります。メンタリングによる厳しい指摘も、優しい寄り添いも、事業をブラッシュアップしていく過程における心の支えとなるそう。
「同じ地区のアトツギ仲間とは楽しく飲むことはあっても、新しい事業を一緒に考える機会はなかなかない」とメンターの存在意義を強調しました。

続く水野さんも「孤独になりそうなときに救っていただいた」と回答。加えて「伝えたいことをたくさん詰め込んだものの、どこを省けばいいかわからないときに、客観的なアドバイスをいただけたこともありがたかった」と語りました。

メンタリングを行う立場として押さえるべきポイントについて語ったのは、窪之内さん。これまでにピッチコンテストに3度出場し、「Forbes JAPAN アワード」や「アトツギアワード2024」のグランプリなどの受賞歴を持つ窪之内さんは、多くの挑戦者たちのメンタリングも行ってきました。
窪之内さんはピッチのポイントについて「大前提として時間内に終わらせることが大切です」と強調し、「起承転結に基づいたストーリー展開も重要ですが、最後に人の心を動かすのはパッションだと思います」と力強く語りました。

アトツギ甲子園経験者が“再出場を熱望”する理由とは?
ピッチコンテスト準備中の苦労話や窪之内さんがメンタリングを行った企業の具体的な事例など、実用的なトピックが飛び交ったSESSKION2もいよいよクロージングに。
スピーカーの皆さんがアトツギ甲子園の出場資格がある方に向けて、自身の体験をもとに熱いメッセージを届けました。
環境大善の窪之内さんは「自社の事業に直接的に大きな影響があるわけではありませんが、やはり事業に自信を持てますし、スタッフたちの向上にもつながります。社長になると、時間内でしっかり話さなければいけない機会は何度でもありますから、その経験を事前にできる素晴らしい場をぜひ活用してほしいですね」と語りました。
山ス伊藤商店の梅木さんは「アトツギ甲子園への出場は、孤独を抱えているアトツギが外に一歩を踏み出すきっかけになります」と自身の経験から出場を後押し。39歳を迎える2025年に、温めてきた事業をテーマにアトツギ甲子園に再出場したいという熱い想いを語りました。
水野染工場の水野さんも「現在29歳なので、あと10年挑戦することができる」と再出場への前向きな意思を表明。「失敗も糧になると考えているので、やるかやらないかで悩んでいたら挑戦してほしいです」とエールを送りました。

モデレーターの山上さんは、「僕たちアトツギは悩みの多さに対して、頑張りが認められにくいところがありますよね」とアトツギの気持ちに寄り添いつつ、「挑戦する姿を見せることで『なんか頑張ってるね』と社員から認めてもらいやすくなる気がします」とピッチコンテストのインナーブランディング効果にも触れ、SESSION2を締めくくりました。
*
続くSESSION3では、「人口減少下の新しいビジネスを縮小する地域経済を突破する挑戦」というテーマでセッションを開催。家業の未来と地域の未来をどのように捉え地域ならではの挑戦をどう進めているのか。アトツギの皆さんにリアルな取り組みを伺いながら、次へのヒントを考えていきます。
人が少ない地域でも、だからこそ、やれることがある。「人口減少下の新しいビジネス~縮小する地域経済を突破する挑戦~」SESSION3レポート
ライター:佐々木ののか
撮影:横井千春
CONTACT
